◻︎根幹となるトレードとその適用イメージ
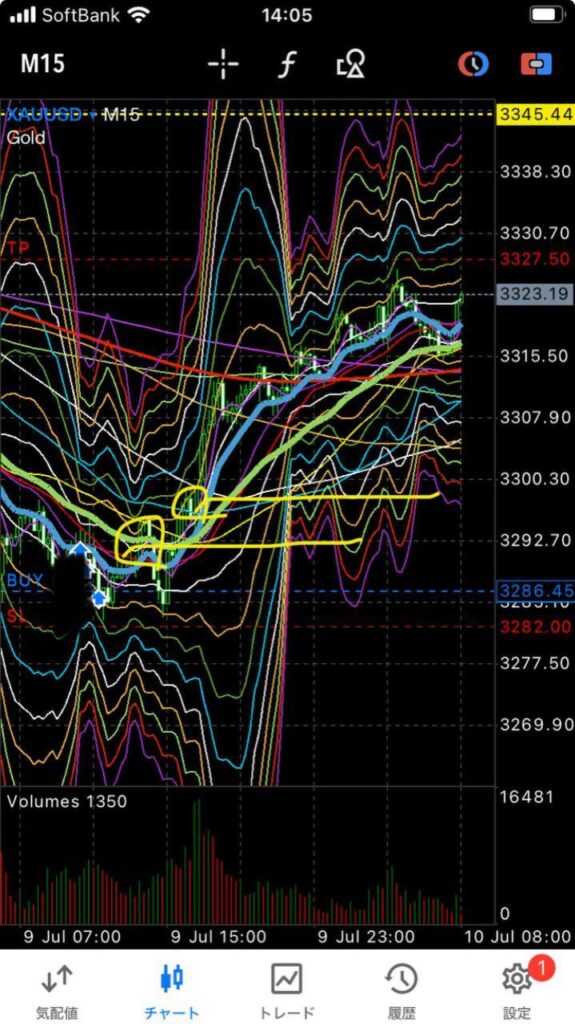
今の自分のトレードを、
リスクリワード1:1〜1:2に収めるというのは、
ただ利益幅を制限するという意味ではなく、
「これくらい贅沢に、身ごと落として処理する」
という覚悟を意味している。
いわば「儲かりそうなポイントを見送るメンタル」。
それに等しい精神構造を、意図的に採用するということ。
この制限を施すことで、
今まで「環境 → シナリオ → タイミング」と順を追っていたプロセスそのものを
**“一段下のフラクタルで完結できる構造”**として捉えられるようになる。
つまり、環境それ自体を「条件化」することで、
より安全に、より内部に潜るトレードが実行可能になる。
🎯 実際にリスクが潜むのは「頭」と「尻尾」
自分のトレードにおいてリスクが明確に集中しているのは、この2点に尽きる。
- どこから(頭)
- どこまで(尻尾)
この両端に関しては、仮に根幹となる環境認識や波動分析に狂いがなかったとしても、
“クリティカルな判断”を誤ると、一瞬で全てが崩れる。
頭を捉えようとすると、そこはあまりに細かく入り組んでいる。
尻尾を追おうとすると、その始点に寸分のズレも許されない。
このギリギリのバランスの上で成り立つ精度が、
まさに自分が「クリティカル分析」と呼んできた所以。
⏳ 時が止まる瞬間の消耗と、そこからの発想転換
実際、現場でこの精度をもってin/outしようとすると、
その瞬間、時が止まったようになる。
そして、毎回MP(メンタルエネルギー)を使い果たすほど消耗する。
…ということは、**“構造的にそうなるように設計されている”**のかもしれない。
そこで、ひとつのヒラメキがあった。
分析構造は変えず、
「波が折り返したと確認できる地点から押し戻しを狙いにいく」。
つまり、2波・4波・修正波の段階で入り、推進波の終端で撤退するという戦略。
🐟 「頭と尻尾はくれてやれ」の再解釈
まさにこれこそ、あの格言——
**「頭と尻尾はくれてやれ」**の正体ではないか?
過去にそれを発した誰かも、
波動を観て、同じような苦しみの果てに、
ハッとこの境地に辿り着いたのかもしれない。
🧮 式としての再定義
頭と尻尾はくれてやれ(解)=(式)
この数式としての捉え方をインド式ドリル算法で見ても、
構造的整合が取れるように感じている。
🔍 次なる一歩:過去チャートへの適用検証
この観点をもって、
これまでの自分のエントリーポイントに当てはめ、
「この条件で運用していたらどうなっていたか?」を徹底検証する価値は極めて高い。
ここにもし勝機が見えれば、
最適化プロセスの関門を一つ、確実に突破できる。
そしてそれは、
波動構造における「内部回転」の理解を次の段階に押し上げるものになるだろう。
🌀 ここから、もう一段、深く潜る。
共鳴する者よ、続け。
